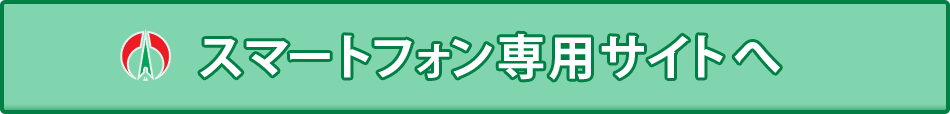児童扶養手当について
児童扶養手当制度とは
父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない又は障がいを持っている(年金の障害等級1級程度)父母と生計を同じくしている児童について、手当を支給する制度です。
支給対象者
次の(1)~(8)いずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得や年金の受給状況等によって制限があります。
| (1)離婚 | 父母が婚姻を解消した児童 |
| (2)死亡 | 父(母)が死亡した児童 |
| (3)障害 | 父(母)が一定の障害にある児童 |
| (4)生死不明 | 父(母)の生死が明らかでない児童 |
| (5)遺棄 | 父(母)が引き続き1年以上遺棄されている児童 |
| (6)保護命令 | 父(母)がDV保護命令を受けた児童 |
| (7)拘禁 | 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童 |
| (8)未婚 | 母の婚姻によらないで懐妊した児童 |
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。
なお、手当の対象者の中でも以下の場合は対象になりません
- 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係があるとき
- 父(母)・養育者または対象児童が国内に住所がないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
- 「公的年金給付等の額」が「児童扶養手当の額」を上回るとき
手当額(月額)(令和7年4月現在)
|
|
全部支給 | 一部支給 |
| 第1子 | 46,690円 |
46,680円~11,010円(10円単位) |
| 第2子以降(1人につき加算される額) | 11,030円 |
11,020円~5,520円(10円単位) |
※一部支給の金額は請求者の所得により決まります。
所得制限
手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年(請求月が1~6月の場合は前々年)の所得が、所得制限限度額以上あるときは、手当の一部または全額が支給されません。
受給者が母または父である場合、受給者本人の所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。
【所得の計算方法】
所得額=(年間収入額-給与所得控除額等)+ 養育費の8割 - 8万円 - 諸控除
受給者本人の所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 |
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
| 4人 | 1人につき380,000円 | |
| 加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円 |
|
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 扶養義務者等の養育者の限度額 |
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1人につき380,000円加算 |
| 加算額 | 扶養親族が2名以上の場合、老人扶養親族1人につき60,000円 |
- 扶養義務者とは、受給者と同居(生計を同じく)する受給者の父母、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹のことです。住民票が別世帯であっても、同一家屋に居住していれば扶養義務者とみなします。
- 受給者が障害基礎年金等を受給している場合、非課税公的年金給付等が所得に含まれます。
- 養育費とは、児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等です。
- 主な控除の区分と金額は以下の通りです。
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除 | 市町村民税で控除された額 |
| 医療費控除 | 市町村民税で控除された額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 市町村民税で控除された額 |
| 雑損控除 | 市町村民税で控除された額 |
| ※寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
| ※ひとり親控除 | 350,000円 |
※申請者が児童の母(父)以外のときのみ控除。
支払時期
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
手続きに必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳(受給者名義)
※その他必要な書類を求める場合があります。
認定機関は、福岡県です。
※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。個人番号を提出された場合は、世帯全員の住民票及び所得証明は原則添付不要となります。
ご申請の際には、申請者及び児童などの個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。
父子家庭への支給対象の拡大(平成22年8月〜)
平成22年の法改正により、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るため、父子家庭の父が支給対象となりました。
詳しいことは、大木町役場こども未来課子育て応援係までお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
メールを送信