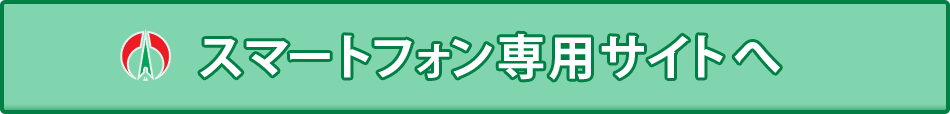おおき昔話
大木町に残る代表的な昔話に大木町語り部絵本「みんなが暮らしの天才だった」の画を組み合わせたページです。
大木町語り部絵本におまけとしてついている「メンコ」とは少し違いますが、あの頃を知らない子どもたちとご一緒に楽しんでください。

今から約2千年以上前、この地方は広々とした有明海の一部だっただろう。今でも堀や土地を深く掘れば、下から牡蠣や貝の殻が多数出てくるのでもわかる。又、牟田という地名は、湿地の意味をあらわしているし、古賀は荒地を意味している。
この土地に、祖先はいつごろ住みつき、開拓してきたのだろうか。誰がいつごろ堀を掘ったのだろうかなど今でもこのような話しがうけ継がれている。

昔、本木(現大川市)に空を突くような大木があったそうな、朝日が昇るとその影は肥前の山を覆ったという。
夕方には、夕方で影が筑後の山や平野を覆いつくしたというほどであった。
ある時、その大木が東に倒れたそうな、そして木のちょうど中ほどが中木という地名になり、木の先にあたるところが木先(木佐木)となったという。その一番頂上を上木先(上木佐木)と呼んだということで、今でも古老の間に話し継がれている。

炊事の水を汲むのに、昔は井戸つるべで汲みあげたものです。ある家で、花嫁さんがお嫁入りしたあけの朝早く、ねえさんかぶりに襷がけで、かいがいしく井戸にゆき、朝餉(あさげ)の支度をするのに、水溜め桶に水を汲みあげていたら、お姑さんがやって来て、水溜桶の底板をぽんとほかして(外して)、さあこの桶に水を溜めなさいと言われたそうです。花嫁さんはおかしなことをなさると思いながら言われたとおりせっせとつるべで水を汲みあげさあーと溜桶に入れても底の無い水桶にはひとつも溜まりません。そうしているところにまたお姑さんが来て、底のある水桶と交換し、こんどはつるべの底をぽいとほかして(外して)から、これで水を汲みあげて溜めなさいと言われたそうです。こんども言われたとおり、なんべんもなんべんも汲んでいたら、つるべと縄についている雫で少しずつ水桶に溜まったそうです。そこでお姑さんがこられて、おっしゃるには「わたしもここにお嫁に来たときに、こんなことをしました」と、そして「これから家のくらしをしてゆくのには、主人がどんなに働き稼いできても、嫁さんが貯める考えがなく、どんどん使えば、この水桶のように一つも貯まりません。収入は少なくとも貯めようと思う気持があって、ほんの僅かでも貯めれば、いつかは桶はいっぱいになりますよ」と、新しい生活のスタートに家訓らしいことを言われたそうです。

城島・横溝町の県道で、今は賑やかになっている大溝小学校付近一帯を提灯林(ちょうちんべし)という。古老の話によれば、昔、この一帯は、森や竹やぶだった。明治の中頃までは、夜暗くなって近くを通ると、提灯を持った人が道案内をしてやるといって、森の中へ連れ込んで、食べ物を持っていると全部取ってしまった。それは狐か狸の仕業だということである。それでこの付近の地名を提灯林(ちょうちんべし)と言うようになった。

江戸も末期の頃、平五郎という人の好い中年男が村に住みはじめて、農家の手伝いなどをして日々を暮らしていた。たまたま一月十四日の正月で酒を饗応され、左義長の藁塚の中で眠っていたらしく、それを知らない村人や子ども達が左義長に火を放ち、平五郎さんは大火傷を負って死んでしまった。それからこの村では左義長を焚かなくなったと古老の言い伝えがある。平五郎の字名の起りもそれからではないかといわれている。

八町牟田下の木本神社のご神体は、昔ある人が、木の本という田んぼで田を耕していたところ、牛に引かせていた鋤(すき)が土の中の軽石にあたって、鋤(すき)の刃がつぶれてしまった。ところがその軽石から赤い血が流れていたので、驚いて拾いあげ、今の神社のご神体として祀ってあると云う。ご神体を祀ってある所の扉を開けて、内を覗き込んだら目がつぶれるとお年寄りの人達から言い伝えられている。今ではいぼの神様として軽石をいっぱい神社にお祀りしてある。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策調整係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1036
ファックス:0944-32-1054
メールを送信