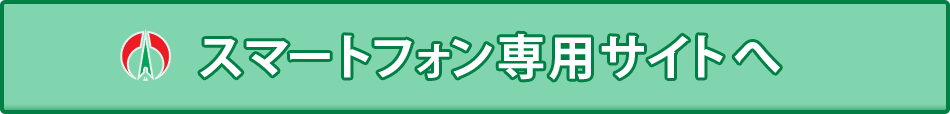大木町の文化財1 町指定文化財
大木町が指定している6つの有形文化財を紹介します。

《大木町指定有形文化財第1号》
大角の六地蔵(おおずみのろくじろう)(大角)
石幢型六体組の六地蔵で、台座(155センチメートル)を含めた全高が225センチメートルという高い塔身が特徴です。三潴郡誌によると明和元年(1764年)に再建奉納され、施主郎心の銘があります。

《大木町指定有形文化財第2号》
高良玉垂命神社鳥居(こうらたまたれのみことじんじゃとりい)(笹渕)
天明9年(1789年)の建造物です。鳥居は神社参道入口に建つ一種の門で、山、川などの自然界の入口に建てられ、その地域が聖域であることを示すものです。鳥居の種類には明神鳥居、神明鳥居、両部鳥居、山王鳥居などがありますが、大木町にある鳥居はほとんどが明神鳥居です。
鳥居の語源については、「鶏が止まり居る横木」「人が通り入る門」など諸説あります。

《大木町指定有形文化財第3号》
清浄院宝篋印塔(しょうじょういんほうきょういんとう)(前牟田)
前牟田西の古刹、清浄院の境内にある、宝暦13年(1763年)建立の宝篋印塔です。院を中興した洞誉上人によって建てられました。
宝篋印塔は「宝筐院陀羅尼経」を納めた供養のための仏塔で、日本では鎌倉時代以降多く作られるようになりました。
清浄院の宝篋印塔の塔身(中央やや下の方形部分)にも、宝筐院陀羅尼経が刻まれています。

《大木町指定有形文化財第4号》
侍島板碑(さむらいじまいたひ)(侍島)
北島氏宅の庭にある、戦国時代の天文2年(1533年)作の板碑です。中央に刻まれている梵字は、八町牟田下の板碑の梵字と同じで阿弥陀如来を表わしています。その下にある右の梵字は観音菩薩を、左の梵字は勢至菩薩を表わしています。半分埋もれていたものを平成11年(1999年)地区の方々が掘り出して整備されたものです。町内の板碑の中では最も古いものです。

《大木町指定有形文化財第5号》
聖塚の板碑(ひじりづかのいたひ)(侍島)
現在は、納骨堂敷地内にありますが、以前は北へ100メートルの地にあった聖塚に建立されていたものを土地改良事業の整地のために現在地に移転したものです。板碑には「奉納陸舎念佛一石、阿弥陀大○名王」「天正三年(1575年)○月○日」とあります。
一部、解読不能の箇所は○で表記しています。

《大木町指定有形文化財第6号》
大藪三島神社手洗い(おおやぶみしまじんじゃてあらい)(大藪)
寛保2年(1742年)作で、大木町の手洗いでは2番目に古いものです。神社の手洗いは、身心を清め、神仏に参拝、礼拝するために設けられたものです。
この記事に関するお問い合わせ先
地域づくり課 学び推進係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1047
ファックス:0944-32-1183
メールを送信