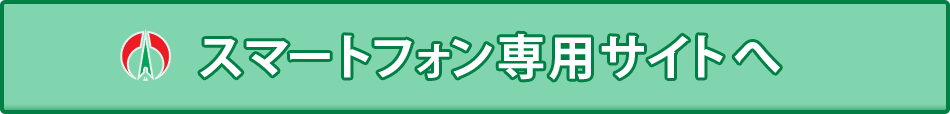大木町で新規就農者を目指す皆様へ

大木町で新規就農者になるためには
大木町で就農をされる方への支援として、大木町新規就農育成支援協議会(大木町、JA福岡大城、南筑後普及指導センターで組織する支援機関)が行う就農相談会、就農のための研修、就農後のサポートを行っています。以下のスケジュールで2~3年ほどかけて就農することが一般的です。
新たに農業を始めるということは、農業というビジネスを開始するということです。農業で生産・販売により利益を追求するためには、「明確なビジョン」「経営感覚」「行動力」が求められます。また、一人で農業をすることは困難なため、家族の同意と協力が必要です。
情報収集を十分にせず、思い付きや憧れ、現実逃避先としての就農を目指しても成功することはありません。家族に迷惑をかけるだけではなく、支援してくれる地域の農業者にも迷惑をかけることになります。
農業を始めるまでには「技術習得」「機械・施設」「農地」「販売先の確保」「地域との関係づくり」など、多くの準備が必要です。計画的に、時間に余裕をもって準備を始めましょう。
農業に向いているか見極める期間(1年程度)
STEP1 相談・情報収集
「大木町で農業を始めたい」と思ったら、まずは就農相談をしましょう。電話・窓口にて随時相談を受付しています。
相談される際には、事前に自分が目指す農業経営のビジョンを明確にしていただくことで、就農に必要な情報などをスムーズに提供を受けることができます。
「農業は儲かるの?」「農業を始めるには何が必要?」など、疑問や質問したいことがありましたら、まずはご相談ください。
●個別相談窓口(対応時間:午前8:30~午後5:15)※要予約
|
JA福岡大城(大木支店) |
住所:福岡県三潴郡大木町八町牟田330 電話:0944-32-1800 |
|
南筑後普及指導センター (地域振興課地域係) |
住所:福岡県みやま市瀬高町下庄800−7 電話:0944-62-4191 |
| 大木町役場(産業振興課) |
住所:福岡県三潴郡大木町八町牟田255−1 電話:0944-32-1063 |
●就農相談会(毎月第2水曜日実施)※要予約
個別相談を受けた方で、必要に応じて就農相談会を実施しています。就農の支援機関である大木町新規就農育成支援協議会(JA、普及センター、大木町)の各機関の担当者が集まり、就農に関する支援を行います。
相談にあたっては、新規就農相談カードと新規就農計画書を記入ください。就農予定地、栽培希望品目、必要とする農地の面積、栽培技術研修の有無など、自身の考えをまとめていただくとより具体的な提案をお話しすることができます。
STEP2 農業体験
漠然としている農業に対する「イメージ」と「現実」のギャップを埋めるため、農業や農村の暮らしを体験しましょう。休暇等を利用して『農業インターンシップ』や『農業体験農園』を受け、自分にとっての将来の具体的な農業経営像(作目、経営形態、就農予定地)をイメージします。
●知り合いの農家にお願いして、休暇等を利用して農作業させてもらう
●農業アルバイトをする
●農業インターンシップ
農業法人で就業体験をする制度です。全国新規就農相談センターは、農業インターンシップを実施しています。
https://hojin.or.jp/agri/agri_category/human/internship/
●農業体験農園
福岡県内には多くの体験農園があり、プロの農家から教えてもらいながら、種まきから収穫までを体験できます。野菜づくりに必要な種や苗、くわなどの農具類は農園で用意されており、定期的に野菜づくりの講習会も開催されています。
STEP3 決断
「農業を始める」ということは、起業して「経営者になる」ということです。決断する前に、以下のことを確認しましょう。
check1.農業のリスクや厳しさを理解していますか?
check2.家族の理解と協力が得られますか?
check3.農村社会で暮らせますか?
check4.農業経営者として自立する覚悟、信念がありますか?
STEP4 計画
自身が目指す農業(営農目標)を明確にし、いつまでに何をしなければならないか整理・計画を行いましょう。
STEP5 研修生面接
大木町新規就農育成支援協議会の研修生として認定を受けるために面接を受けます。
研修生となることで、協議会の研修カリキュラムの受講や、就農準備資金を受給することができます。
農業経営者としての自立に向けた農家・法人等での研修(1~2年)
STEP6 就農準備研修
自身が選択した品目に合う研修先で1~2年間、就農に向けた研修を行いましょう。栽培技術・経営管理について「播種から収穫まで」を最低1サイクル以上学んでおくことが必要です。
●新規就農で選ばれている主な農作物
いちご・・・6月~翌年5月に研修
アスパラガス・・・1月~12月に研修
●研修先
先進農家・法人等(大木町新規就農育成支援協議会で研修の支援をします。)
●資金などの手当て
就農希望者のうち、大木町新規就農育成支援協議会の研修を受ける人で研修資金を希望される方は受給ができます。
| 就農準備資金(新規就農者育成支援総合対策)※国庫補助 | |
| 対象 | 大木町新規就農育成支援協議会の研修を受ける就農希望者 |
| 要件 |
1.就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること 2.研修計画が以下の基準に適合していること a.就農に向けて必要な技術等を修得できる研修機関等であると都道府県等が認めた研修機関等で研修を受けること b.研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること 3.常勤の雇用契約を締結していないこと 4.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと 5.研修終了後に親元就農する予定の場合にあっては、家族経営協定等により交付対象者の責任や役割を明確にすること、及び就農後5年以内に当該農業経営を継承し、または当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者・親族との協同経営者とすることを確約すること 6.研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けること |
| 返還 |
1.適切な研修を行っていない場合 給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 2.研修終了後1年以内(※)に原則50歳未満で就農をしなかった場合 ※受給終了後、原則2年以内で対象となる研修に準ずる継続研修を行う場合は、継続研修終了後1年以内 3.給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合 4.親元就農者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合 5.独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けなかった場合 |
STEP7 営農計画を立てる
これから行う農業を具体的に営農計画として作成します。5~10年後までの農業経営の発展過程をより具体的に描くことが大切です。計画を作成することで、準備が必要なことや足りない部分が明確になります。
|
資金 |
調達先、担保・保証人 |
|
農地 |
購入(借入)先、購入(借入時期)、借入期間、地代 |
|
生産 |
作目・品種構成、生産規模、目標生産量・品質 |
|
労働力 |
作業の時期・内容、繁忙期の雇用の有無 |
|
機械・施設 |
種類、導入方法 |
|
販売 |
販売先、販売方法、販売単価、販売量、代金の回収 |
|
収支 |
収支計算、資金繰り、生活費、税金 |
いちご・アスパラガスの初期投資費用の目安 (PDFファイル: 68.3KB)
STEP8 就農に必要なものの確保
1.農地の確保
最初に課題となるのが農地の確保です。農地は売買より賃借により取得し、営農開始するのが一般的です。農地中間管理事業による農用地借受希望者の募集が定期的に実施されていますので、詳細については大木町農業委員会までお問合せください。
2.住宅の確保
農産物の適切な管理を行うためには、できるだけ住宅は農地に近いほうが望ましいです。町では、空き家などの物件の情報を提供していますが、作業場や倉庫も備えた良い条件の物件は、なかなか見つからないのが現状です。地域の人との信頼関係を気付き、地域の人たちの協力を得ることも大切です。
※町外から転入される方には、転入支援のための町の補助金があります。
3.機械・施設の確保
初期投資をいかに抑えるかが事業の成功のポイントです。新規就農の場合、全ての機械や施設を一度に揃えようとすると多額の資金を要します。当初は必要最低限の機械・施設でスタートし、機械を借りることができないか、中古機械、遊休農地について、こまめに情報収集を行いましょう。
4.資金の確保
新規就農の場合には、収益がでるまでの2~3年間の生活資金や運転資金に多額の資金を要します。給付金や制度資金の活用も可能ですが、可能な限り自己資金を準備することが基本です。
就農(営農開始)
研修機関終了後、認定新規就農者として認められれば、いよいよ経営が開始します。
認定新規就農者になることで、独立するための開業資金として国や県、町から様々な補助を受けることができ、就農に必要な土地や機材を揃えることができます。
●認定新規就農者制度について
認定新規就農者制度は、市町村が策定する基本構想に示された農業経営の目標に向けて、新たに農業を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、重点的に支援措置を講じるものです。
(1)青年等就農計画の対象者
市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市町村から認定を受けることを希望する者
(2)認定の基準
1.その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
2.その計画が達成される見込みが確実であること
農林水産省:青年等就農計画制度について
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html
●資金・融資
| 経営開始資金(新規就農者育成総合対策)※国庫補助 | |
|
対象者 |
認定新規就農者(50歳未満) |
|
事業内容 |
就農直後の経営確立のための経営開始資金の交付 |
|
助成内容 |
12.5万円/月(年間150万円)×最大3年間 ※夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付 |
| 経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)※国庫補助 | |
|
対象者 |
認定新規就農者(50歳未満) |
|
事業内容 |
就農に必要な農業用施設・機械の整備 |
|
助成内容 |
[標準事業費]1,000万円※ ※夫婦ともに就農する場合は、補助上限額の1.5倍を上限 |
| 青年等就農資金 | |
|
貸付対象事業 |
農地の改良、施設、機械の取得・改良等 |
|
貸付対象者 |
認定新規就農者(経営開5年以内) |
|
貸付限度額 |
3,700万円(融資立100%) |
|
利率(年利) |
無利子 |
|
償還期限(据置期間) |
17年以内(5年以内) |
|
融資機関 |
日本政策金融公庫 |
大木町で受けられる補助金一覧 (PDFファイル: 103.2KB)
●参考資料
大木町新規就農支援協議会では、新規就農を考えている人向けに、新規就農支援マニュアルを作成しています。
新規就農者の声
大木町に新規就農した方々へのインタビューをお届け! なぜこの農業を選んだのか、そのきっかけや、実際に就農開始してからのエピソードなど、様々なお話をお伺いしました。
立石 宜丈さん、みどりさん ご夫婦 (2020年就農)
品目:いちご

Q.新規就農を志したきっかけはなんですか?
A.30代の頃、40代になったら独立しようと模索していまして、元々興味があった農業を妻の出身地である福岡県でやろうと決め、(公財)福岡県農業振興推進機構の新規就農相談窓口に相談に伺い、大木町にある、いちご研修施設の株式会社NJアグリサポートを紹介していただきました。
株式会社NJアグリサポートでの研修が終わって経営開始した後も研修施設や先生、卒業生からサポートやアドバイスをしていただき、とても感謝しています。
Q.就農して感じたことはありましたか?
A.大変だったことを一つ挙げるとしたら、いちごの生産ができる体制を作ることですね。農地探し、ハウスの仕様や配置、スタッフの募集•育成、道具を揃えたり、様々な手続き等々、数え上げたらキリがないです。エキサイティングな1年でした。いろんな方に助けられて1年を乗り切ることができました。
逆に、就農してよかったことはたくさんあります。
一つは、地域とのかかわりを増やすことができたことです。先輩農家や農協の方々、ハウス近隣にお住まいの方々等に積極的に挨拶したことで交流の輪が広がり、為になる話を聞くことができたり、困った時に相談することができています。
また、会社員時代は家庭で仕事の話はあまりしなかったのですが、今は、夫婦で同じ仕事なので妻と共通の話題ができ、たまに喧嘩したりもしますが、これまで以上に夫婦仲が良くなり、絆が深まりました。
Q.これからの新規就農者に伝えたいことは何かありますか?
A. 1計画性を持った資金の使い方をする
2今の産地を築いてきた先輩農家や就農までに携わった関係機関への感謝
3情熱をもって農業に取り組む
Q.立石さんにとって農業とはなんですか?
A.一言で表すと「毎日が運動会♪」です。収穫の時にハウスを開けるといちごがズラーっと赤くなっているのを見ると「今日も忙しくなるぞ!」と嬉しくなります。お天道様の下で自分が育てた作物を収穫できる仕事は、私にとって最高の仕事です。そして、仕事後にいただくビールがおいしいです!



この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農地・担い手係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
メールを送信