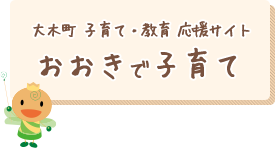乳幼児等予防接種
赤ちゃんやこどもは、大人のようには病気に対する抵抗力が完全にできあがっておらず、おかあさんが赤ちゃんにプレゼントした、病気に対する免疫は生後3か月から徐々に失われていきます。感染症にかかると、大人では考えられないような重い症状となることがあります。そのため、この時期を過ぎるとこども自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けになるのが予防接種です。
こどもの予防接種は種類、回数も多く、それぞれ適した年齢がありますので、その年齢に合わせて接種できるよう、かかりつけ医を決め、なるべく早い時期に、お子さんが、体調が良いときに受けられるようお勧めします。
こどもは発育をともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さまの健康にお役立てください。
予防接種の種類
予防接種には、定期予防接種と任意予防接種があります。
定期予防接種とは
法定期予防接種とは法律(予防接種法)に定められているワクチン接種を、定められた期間(年齢)に行うことを指します。接種費用は定められた期間中であれば無料(全額公費負担)です。
任意予防接種とは
任意予防接種とは法律(予防接種法)での定めはなく、ワクチンのことをよく理解し、接種を希望した場合に接種できます。「おたふくかぜ」はこれにあたり、接種費用は全額自己負担となります。
●ワクチンの種類
・ 5種混合ワクチン(Wordファイル:47.6KB)
・ ロタウィルスワクチン(Wordファイル:157.6KB)
・ B型肝炎ワクチン(Wordファイル:13.5KB)
・ 肺炎球菌ワクチン(Wordファイル:105.9KB)
・ BCG(Wordファイル:19.5KB)
・ 麻しん・風しん(Wordファイル:26.6KB)
・水痘(みずぼうそう)(Wordファイル:30.9KB)
・日本脳炎(Wordファイル:44.7KB)
・二種混合(Wordファイル:264.5KB)(Wordファイル:62.5KB)
・ ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頚がん)(Wordファイル:264.5KB)
● 定期予防接種一覧表
● 定期予防接種一覧表 (Excelファイル:17.4KB)
● 詳しい内容はこちら ⇒ 
注意事項
● 予防接種を受ける前の注意事項
赤ちゃん訪問や転入時の際にお渡しした「予防接種セット」に同封されている「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、ワクチンについてよく理解しておきましょう。
・おお子さんの体調の良いときに接種するようにしてください(体温37.5度以上は接種できません)
・予診票は保護者が責任もって記入してください
・接種当日はお子さんの健康状態がわかる保護者が同伴するようにしてください。保護者以外が同伴する場合は委任状が必要です。委任状はダウンロードできます。
●持ち物
1.母子健康手帳(ない場合は接種できません)
2.予診票(記入のうえ医療機関へお持ちください)
※予診票が手元にない場合は、医療機関・こども家庭センターにもあります
3.住所、年齢、氏名が確認できるもの
●予防接種を受けたあとの注意事項
・接種当日の重い副反応として、まれにアナフィラキシー症状が起こる可能性があります。予防接種を受けたあとの30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう
・接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう
・接種部位を清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう
・接種当日は、激しい運動は避けましょう。
・接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう
接種医療機関
1年中接種可能ですが、事前に実施医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)のうえ、接種してください。
予防接種受託医療機関 (Excelファイル: 43.5KB)
●予防接種による健康被害救済制度について
定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども家庭センター
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1022
メールを送信